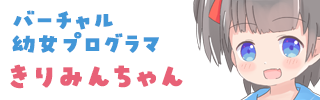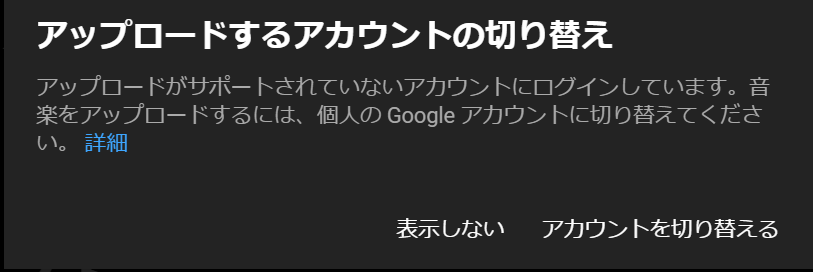の続き的な。
ブログを2つに分ける必要性についていつも考えて微妙な気持ちになる。
スキル
最近はWebフロントエンドを中心に仕事してる。(Next.js)
バックエンドも少しやってる。(NestJS)
右も左も分からないという感じのまま、一人でWebアプリのフロントを一通り実装したりした。
一応求められている機能を実装することはなんとか出来ている。最近はChatGPTやGitHubCopilotもあるし、局所的な課題はまあなんとか解決出来る。ReactやNext.jsの基礎もまあ一通りは学習してる。(すぐに忘れてしまうため人に聞かれてもすぐに答えられないような知識の濃度だが)
ただ、フロントエンドでのコーディングや設計のベストプラクティスだとか、Web環境の細かい仕様といった部分はなかなか一人ではキャッチアップ出来ない。いや、多分賢い人は出来るんだろうけど、自分にはなかなかそういうところまで情報収集する力が足りていない。
幸い、自分より詳しい人が新しく入ることになったので、今後は色々学んでいけるかもしれない。
それにしても今の職場には学生や社会人数年目で自分よりずっと若いけどフロントエンドもバックエンドもバリバリ出来るという人が多くいる。
一方自分は30代だがフロントエンドもバックエンドもインフラも1年生という感じだ。正直、もう少しAndroid開発でのキャリアや今まで勉強してきたことが活かせると思っていたが、全然駄目だった。ずっと薄々危惧していたとおり、Androidを除いた自分の技術力はせいぜいちょっと出来る新卒くらいのものだった。
もちろん環境との相性とかもあって、もう少しビジネススキルの比重が大きい現場であれば能力を発揮出来る場面もあるかもしれないが、今働いている環境ではあまり上手くやれていない。
キャリア
技術力とは何か、ということをAndroidエンジニアをやっていた10年間もずっと漠然と悩んでいたが、結局汎用的な技術というのはあまり身につかないまま来てしまった。
Androidエンジニアを出来る限りずっとやっていた方が幸せだったんじゃないかとか、むしろもっとはやくフロントエンド、バックエンドの海原に飛び出すべきだったんじゃないかとか色々ぐるぐると考えてしまう。
しかし過去は変えられないし、今後のことを考えるとやはり自分は一度フルスタックにスキルを伸ばしていきたいと思う。やっていけるんだろうか。正直、この経歴で今また新人レベルのスキルとして仕事をしてるというのは自尊心的にはちょっと辛いしもどかしい気持ちがわりとある。
今後、どんな方法でどんなことを勉強していけばもっと優秀なエンジニアになれるのだろうか。自分を引っ張ってくれるようなロールモデルがいればいいんだけど。
体力
もっと頑張りたいという気持ちに対して、体力とメンタルという2つの壁が立ちはだかる。
仕事に復帰しても、コロナ禍前の頃のような体力はつかず、時短勤務をしていても毎日眠くて仕方がないし、土日もどこかへ出掛けたり何かをしたりという気力がなかなか湧いてこない。
メンタルも最近はかなり低空飛行で特に大きな理由がなくても不安と息苦しさに押しつぶされそうになる。もう自分の人生は何もかも駄目なんじゃないかと感じたり、全てを終わらせて楽になりたいと考えたりしてしまう。
改善のために運動や筋トレをした方がいいとは思っていても、それを継続するだけの心の余裕がまず捻出できないという状態だ。
ある日突然、魔法のような薬が開発されて全てが楽になる日が来ないだろうかということばかり考えてしまう。
雑記
出社可能、週3くらい、そして上に書いたようなスキルレベルでのフロント&バックエンドの仕事というのはかなり探すのが難しいという予感がしている。
特にこの中で出社可能という条件が一番むずかしいというのが辛い。
せめてもっと体力やメンタルが回復して、週5正社員でも耐えられるようになったり、リモート無理なのを克服出来ればいいんだが...と相変わらず悩んでいる。
そんな近況です。
誰かとこういうキャリアとかの話を対面でして「あー分かるー」とか言い合いたいな...。